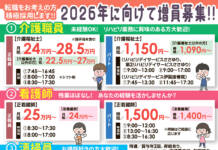【本山さん(左)とともに濡れ地蔵を紹介する中学生たち】
奈良県宇陀市榛原山辺三にある榛原ふれあい広場の一角に、水の中から姿を現す「濡れ地蔵」が佇んでいる。今年も6月から、その姿を拝めるようになっている。

濡れ地蔵は、全体の高さが約180センチで、像自体は約130センチ。「建長六年甲寅八月十五日建」の銘が刻まれていることから、鎌倉時代中期の1254年に造られたと判明している。左手に宝球、右手に鎖杖を持つ半身彫りの立像で、光背は舟形に彫られている。
1974年、室生ダムの完成によって、地蔵の周囲はダム湖の一部となった。それ以来、水位の変動により、地蔵は水中に沈んだり、姿を現したりするようになった。
室生ダム管理所の本山優士さん(32)によると、毎年10月から5月末までは周囲の木々とともに水没し、地蔵の頭上1㍍ほどまで水に浸かるという。
ところが、名前の由来はダム湖に沈むことからではない。背後の山から湧き出す水に常に濡れていたため、古くから濡れ地蔵と呼ばれていたと言われている。
本山さんは「初夏から秋にかけて、花を手向けたり、掃除したりする方が訪れているようだ」と話す。春には広場で「濡れ地蔵桜まつり」も開催され、地元の人々に親しまれている。
ダム管理所では、子ども向けの資料に濡れ地蔵をモチーフとしたキャラクターを登場させている。短文投稿サイト「X(エックス)」でもその存在を発信している。
※この記事は、6月11から13日まで株式会社ユーで職場体験に取り組んだ、名張中学校3年の中原さんと中林さんが取材しました。
- 広告 -