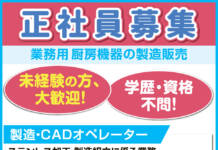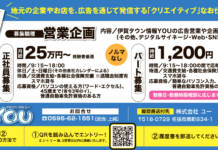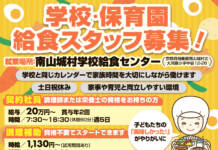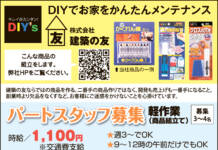【蚕の繭を集める谷口さん=伊賀市北山で】
「虫刺繍作家」として活動する三重県伊賀市北山の谷口聖子さん(54)は、昔ながらの方法で養蚕に取り組んでいる。今年で2回目となる秋蚕に挑戦し、約300個の繭を収穫した。

蚕の習性生かし飼育
大阪府出身で、幼いころから虫の観察が好きだった。18年前、ペットの爬虫類の餌としてシルクワームを購入したのをきっかけに、蚕の飼育に魅了された。兵庫県丹波篠山市の養蚕農家に学んだ後、2018年に伊賀市内の古民家を購入して移住。3年後には約80本の桑を畑に植え、本格的に養蚕を開始した。
卵は業者から仕入れ、孵化後は、無農薬で育てた柔らかい桑の葉を与える。葉を上からかぶせると、蚕は習性に従って上に進み、掃除の手間が減るという。
温度・湿度管理 消毒も徹底
4度の脱皮を経た蚕は、繭作り専用の道具「蔟(まぶし)」に移す「上蔟(じょうぞく)」の時期を迎える。それまでは天気予報を確認して温度や湿度を管理し、毎日欠かさず記録を付ける。
飼育室では靴を履き替え、手洗いや消毒を徹底。他の種類のガに触れないようにし、菌に弱い蚕を守るために納豆すら口にしないそうだ。
近年はつり下げ型の蔟が主流だが、谷口さんは台の上に置く蔟や枯れ笹を使う。「中には台の縁などで繭作りを始める自由な蚕もいる」と笑う。それぞれの蚕が作り出した繭の色や形、光の反射、つや感などにほれぼれするという。
収穫した繭は冷凍し、煮て表面を柔らかくしてから糸取りを行う。糸は染織家の夫・芳國さん(57)が作品に使い、さなぎは乾燥させてから小動物の餌にする。「頂く命は、ちょっとでも無駄にしたらあかん」と谷口さんは静かに語る。
「蚕は自然にはない、神秘的な部分がある」。人の手がなければ生きられず、失敗すれば胸が痛む。だからこそ、どうすれば良い繭を得られるのか勉強を重ねる日々だ。「来春は1500から2000個に挑戦し、育てた繭を使って夫とワークショップも開きたい」と意欲を語った。